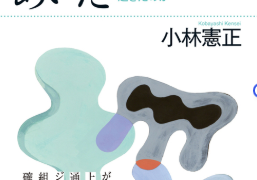生命科学
生命科学20世紀の王道シナリオが「あり得ない」とひっくり返された…なんと、ミラーの「衝撃的実験」に惑星科学の進展が「再検討」を迫った
20世紀の王道シナリオが「あり得ない」とひっくり返された…なんと、ミラーの「衝撃的実験」に惑星科学の進展が「再検討」を迫った「地球最初の生命はRNAワールドから生まれた」圧倒的人気を誇るこのシナリオには、困った問題があります。生命が存在しない原始の地球でRNAの材料が正しくつながり「完成品」となる確率は、かぎりなくゼロに近いのです。ならば、生命はなぜできたのでしょうか?この難題を「神の仕業」とせず合理的に考えるために、著者が提唱するのが「生命起源」のセカンド・オピニオン。そのスリリングな解釈をわかりやすくまとめたのが、アストロバイオロジーの第一人者として知られる小林憲正氏の『生命と非生命のあいだ』です。本書刊行を記念して、その読みどころを、数回にわたってご紹介しています。今回は、RNAだけを用いて代謝も自己複製も行う生命による「RNAワールド」仮説、その誕生の様子を見てみます。*本記事は、『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。ニワトリが先か、タマゴが先か「ニワトリが先か、タマゴが先か」という問題があることは、みなさんも聞いた...